 |
||||||
       |
||||||
|
|
||||||
| 【三百諸藩の幕末の動向】東北の諸藩/関東の諸藩/東海の諸藩/甲信越の諸藩/北陸の諸藩/近畿の諸藩/中国の諸藩/四国の諸藩/九州北部の諸藩/九州南部の諸藩 【その他リストなど】幕末明治の艦艇/御三卿・幕府直轄地拠点/幕末人物 墓所訪問 【晋作の愛した下関】豊北町・豊浦町/豊田町・菊川町/吉母・吉見・福江/向日・井田・田倉/吉田・清末/安岡・綾羅木・延行/長府/市街(下関〜唐戸)/彦島 |
||||||
| -幕末維新入門- | ||||||
|
|
|
|
|
| -幕末維新とは- 幕末維新とは、日本の歴史の一時代です。諸説ありますが、江戸時代の末期(幕末)から明治時代の始め(明治維新)頃で、一般的に嘉永6年(1853)の黒船来航から、明治10年(1877)の西南戦争までの24年間を指します。 |
 ■黒船来航 |
|
|
|
| -どういう時代?- 約260年続いた徳川将軍家の統治した時代から、天皇を中心とした新しい国家体制に移行した時代でした。それは広義には革命と呼べる動きでしたが、日本独自の文化による国家体制の移行によってもたらされた政権交代で、維新という言葉で表されます。 |
 ■明治天皇の東京行幸 |
|
|
|
| -キーワードは不平等- 戦国時代の戦乱に終止符を打った徳川幕府は、約260年続く太平の世です。しかしそれは、士農工商に代表される身分制度をもとにした、細かな階級の作られた不平等の階級社会でした。また鎖国政策をとって外国への門を閉ざし、「神の下に人は平等」という教えを説くキリスト教を禁止します。そして260年間、日本は徳川幕府の鎖国政策と階級制度によって運営されました。そんな中、ペリー艦隊が浦賀に来航。黒船と大砲で威嚇し、開国を迫ります。弱腰の幕府は、米国と不平等な条約を結びました。 |
 ■長崎出島 |
|
|
|
| -尊皇攘夷運動- やがて日本各地で、幕府を非難する尊皇攘夷運動がおこります。尊皇(元来日本は、天皇によって治められた国家である。将軍は天皇の命によって国家運営を委託されたもので、天皇の権威を尊ぶべきである)思想と攘夷(神の国日本から、外国人を排除するべき)思想が合体したこの運動を実行する志士(活動家)達が現れます。彼らは、江戸や京都を中心に活動しました。 |
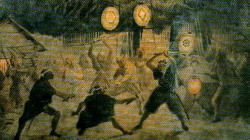 ■攘夷 |
|
|
|
| -安政の大獄と桜田門外の変- この難局の中、彦根藩主井伊直弼が大老に就任します。井伊は、無勅許の条約調印と徳川家茂の将軍継嗣指名を断行して反対派から非難されますが、井伊は反対派を隠居謹慎に処して弾圧を開始しました(安政の大獄)。弾圧は幕府を非難する藩主、公卿、志士に至るまで及びます。この断行に対して、水戸藩、薩摩藩の脱藩浪士が井伊の暗殺を実行しました(桜田門外の変)。この事件によって、幕府の権威は大きく失墜し、尊皇攘夷運動は激化していきます。 |
 ■桜田門外の変 |
|
|
|
| -京都情勢- やがて天皇のお膝元である京都に、志士達が集まりだしました。京都は、徳川幕府からの影響から開放された無秩序な社会が形成され、志士達による天誅が横行します。また食い扶持を求めた浪人たちも、志士を名乗って京都に集まりだしました。そこで幕府は乱れた京の秩序を回復させるために、会津藩主松平容保を京都守護職に任命します。会津藩は、藩兵1000人を京都に常駐させ、江戸から京都に上ってきた浪士組(後の新選組)や、旗本で組織された京都見廻組を預かって、京都の治安維持に努めます。 |
 ■新撰組壬生屯所 |
|
|
|
| -八月十八日の政変- 長州藩は、朝廷とのパイプが太く尊皇攘夷運動が盛んでした。長州藩は、そのパイプを活かして公卿に取り入って朝廷を牛耳り、偽の詔勅を作って幕府に攘夷を実行させることを約束させます。この長州藩の横行に対して、反長州派の公卿と京都守護職である会津藩、京都での実権を握りたい薩摩藩が手を組み、長州藩の朝廷からの締め出しを実行しました(八月十八日の政変)。その結果、長州系の公卿7人が京都を追われて長州に落ちます。 |
 ■七卿落ち |
|
|
|
| -天狗党の乱- 水戸藩の尊皇攘夷派藩士たち(天狗党)は、幕府に攘夷を求めて筑波山で挙兵。日光東照宮を占拠して攘夷を訴える手はずでしたが、幕軍に阻まれ断念します。幕軍は関東諸藩に討伐を命じ、天狗党は戦闘を繰り返しながら西上。京都を目標に進軍しますが、包囲網が狭められ追い詰められた天狗党は投降します。その後、投降した1/3以上が斬首されました。 |
 ■天狗党の乱 |
|
|
|
| -天誅組の変- 土佐脱藩浪士吉村寅太郎らは、攘夷派公卿中山忠光を主将に据えて大和で挙兵して天誅組と名乗ります。天皇の大和行幸の先鋒となるべく、五条の代官所を襲撃しました。しかし京都で八月十八日の政変がおこり、後ろ盾を失った天誅組は暴徒とされて追討の命が下されます。途中、十津川郷士を味方に引き入れますが、追討軍との交戦で疲弊。離脱する者が跡をたたず、次第に追い詰められ壊滅しました。 |
 ■天誅組の変 |
|
|
|
| -禁門の変- 京都から追い出された長州藩は京都近くに出兵。朝廷に復権を嘆願しますが、受け入れられません。そんな中、長州系志士の集まっていた池田屋を新選組が襲撃(池田屋事件)。それを知って激怒した長州兵は、京都へ進軍して会津藩・薩摩藩と激突します(禁門の変)。激戦の末、長州兵は敗退して多くの戦死者を出し、京都市中約3万戸が焼失しました。この戦いによって、長州藩は朝敵となります。 |
 ■禁門の変 |
|
|
|
| -薩英戦争と下関戦争- 薩摩藩の国父島津久光の行列を横切った英国人に対し、藩士が斬りつけて殺傷した事件(生麦事件)の報復として、英国は薩摩湾に侵攻し薩英戦争が勃発します。この戦争は事実上引き分けの形になりましたが、一連の顛末の末に薩摩と英国は友好関係を結びました。また、攘夷決行として関門海峡を通航する外国船に砲撃を加えていた長州藩に対して、英米仏蘭の連合艦隊が下関を砲撃します。惨敗した長州藩は高杉晋作を講和条約の使者として派遣。外国船砲撃の責任は、幕府にあるとして賠償金を幕府に支払わせました。 |
 ■薩英戦争 |
|
|
|
| -第一次長州征伐- 幕府は、朝敵となった長州藩に対して大群を差し向けます。この動きに対し長州藩内部では、俗論派が台頭して幕府に徹底した謝罪恭順の方針を進める。禁門の変に参加した三家老の切腹、山口政事堂の破棄、三条実美ら五卿の他藩移動を条件に、幕府は撤兵しました。 |
 ■山口政事堂 |
|
|
|
| -功山寺挙兵- 幕府に対する徹底した恭順に対して、高杉晋作は功山寺にて挙兵して軍事クーデターをおこします。はじめは80人程度の兵力でしたが、次第に長州藩内の諸隊が呼応。大田絵堂の戦いにおいて藩の正規軍を打ち破り、藩論を倒幕に統一しました。 |
 ■高杉晋作回天義挙像 |
|
|
|
| -薩長同盟- 薩摩藩は、公武合体派の旗手として雄藩連合を構想していたが、次第に倒幕の方向に進んでいきます。しかし薩摩一藩では倒幕は不可能であり、共に倒幕を成し遂げる友藩が必要でした。また長州藩でも、来たるべき幕府との戦争に向けて軍備を進める上で、外国製の最新兵器を揃える必要がありましたが、長州藩は交易ルートを持っていません。禁門の変以降、この両藩は敵対関係でしたが坂本龍馬や中岡慎太郎らの仲立ちにより、薩長両藩は和睦にこぎつけ同盟を結びます。 |
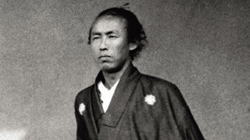 ■坂本龍馬 |
|
|
|
| -第二次長州征伐- 長州再軍備を警戒した幕府は、再び長州征伐にのりだします。全国の諸藩に命じて長州藩領を四方面(石州口、芸州口、大島口、小倉口)から侵攻させます。長州藩は、大村益次郎を総司令官として迎撃します。士気と戦術、装備に優れた長州藩は、各地で幕軍を退けて勝利します。幕府はこの敗戦によって権威を失い、全国に倒幕の気運が高まります。 |
 ■小倉口の戦い |
|
|
|
| -将軍の死去と天皇の崩御- 第二次長州征伐の最中、第14代将軍徳川家茂が死去。将軍後見職の徳川慶喜が、第15代将軍となります。そしてその5ヵ月後には、孝明天皇が崩御されます。公武両方のトップが相次いで亡くなり、政局は混乱してゆきます。 |
 ■孝明天皇御陵 |
|
|
|
| -大政奉還- 雄藩連合設立のため、薩摩藩、福井藩、土佐藩、宇和島藩と将軍によって諸問題を協議しますが、将軍慶喜の政治力が勝り、幕府が主導権を握ります。この状況を打開するために薩長は武力討伐の方針を固めます。その動きを察した慶喜は、先手を打って大政奉還を奏請して、倒幕の大義名分を失わせました。 |
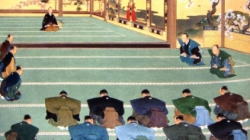 ■大政奉還 |
|
|
|
| -王政復古の大号令- 大政を奉還して幕府を終わらせても、徳川宗家の力は絶大でした。現時点で朝廷に政治を司る力は無く、事実上徳川宗家による支配は変わりません。この状況に対して、公卿の岩倉具視や薩摩藩の大久保利通らは王政復古の大号令を発して、幕府・摂政・関白等の廃止と三職の設置による新政府の樹立を宣言します。 |
 ■小御所会議 |
|
|
|
| -鳥羽伏見の戦い- 新政府は、徳川慶喜に辞官および領地返上をせまります。旧幕府方からすれば到底飲める条件ではありませんでした。また、薩摩藩は息のかかった浪士達に江戸で騒乱を起こさせます。この一連の挑発で、大坂に駐留する旧幕府軍は激高し、京都に向けて進発しました。薩摩軍はこれを鳥羽・伏見で迎え撃ちます。 |
 ■鳥羽伏見の戦い |
|
|
|
| -錦の御旗- 旧幕府軍は、狭い街道での戦闘で優位な兵力を生かすことが出来ず、新政府軍の弾幕射撃によって前進を阻まれます。やがて仁和寺宮嘉彰親王が征討大将軍として参戦し、錦の御旗が戦場に翻ります。これにより新政府軍は官軍となり、旧幕府軍の一員であった淀藩や津藩は新政府軍に恭順しました。旧幕府軍は錦の御旗と裏切りによって総崩れとなり大坂に退却します。 |
 ■錦の御旗 |
|
|
|
| -徳川慶喜の逃亡- 旧幕府軍は大坂城での徹底交戦の構えを見せたが、徳川慶喜はひそかに大坂城を脱出します。取り残された旧幕府軍は戦意を失い、大坂城を放棄して各自に江戸や自領へと引きあげました。やがて慶喜は朝敵となり、慶喜追討令が出されます。 |
 ■大坂城 |
|
|
|
| -慶喜の恭順- 江戸へ帰った慶喜は、徹底交戦派の幕臣を罷免して自ら謹慎して新政府と戦う意思が無いことを示します。一方、新政府は有栖川宮熾仁親王を東征大総督として、東海道軍・東山道軍・北陸道軍の3軍に別れ江戸へ向けて進軍しました。 |
 ■東征 |
|
|
|
| -甲陽鎮撫隊- 江戸に戻っていた新撰組の近藤勇は、天領の甲州を新政府より先に押さえるため、幕軍残党を甲陽鎮撫隊としてまとめ、甲府城を目指します。しかし、道中時間を浪費したことから先に新政府軍に甲府城をとられ、甲州勝沼で新政府軍と戦いました。甲陽鎮撫隊は、兵の逃亡や新政府軍の最新兵器の前に敗れます。近藤は、新政府軍に投降して斬首されました。 |
 ■勝沼駅近藤勇驍勇之図 |
|
|
|
| -江戸城無血開城- 江戸に迫る新政府軍に対して、勝海舟は主戦派を退けて江戸城を明け渡すことを決めます。薩摩出身の天璋院や朝廷出身の和宮ら大奥の嘆願や山岡鉄舟らの工作により、勝と西郷隆盛の会談が実現します。江戸城明け渡しの条件を話し合われ、新政府は血を流さずに江戸城に入城することができました。 |
 ■江戸開城談判 |
|
|
|
| -上野戦争- 江戸城は明け渡されましたが、その処置に不満のある旧幕府兵は、彰義隊を結成して上野の山に立てこもります。この彰義隊に対して新政府軍は、大村益次郎の指揮でこれを鎮圧します。この戦いにより、旧幕府抗戦派は江戸近辺から一掃されました。 |
 ■上野戦争 |
|
|
|
| -会庄同盟- 会津藩は、京都守護職として京都の治安にあたり、京都見廻組や新撰組を使って尊王志士の弾圧を行い、鳥羽伏見の旧幕軍の主力であったために朝敵とされました。一方、庄内藩は江戸で薩摩藩邸の焼き討ちを行っていたために、会津藩と同様の処遇となることが明白でした。このために両藩は同盟して新政府に対抗することとなります。 |
 ■庄内 |
|
|
|
| -奥羽越列藩同盟- 新政府は東北諸藩に会津藩の追討を命じます。新政府は庄内藩にも会津追討を命じますが、庄内藩はこれを拒否します。東北の雄藩仙台藩は、会津藩の赦免を新政府に嘆願しますが拒否されます。そんな中、新政府軍の軍監世良修蔵が書いた「奥州皆敵」の文書が発見され、東北や北越の諸藩は同盟を結んで新政府に対抗する方針を決めます。 |
 ■奥羽越列藩同盟旗 |
|
|
|
| -北越戦争- 越後の長岡藩は中立な立場を取っていましたが、新政府の高圧的態度に対して戦うことを決意し、近隣諸藩6藩と共に奥羽越列藩同盟に加盟します。長岡藩は小藩ながら家老河井継之助に率いられて善戦しました。新政府軍は最終的に勝利しますが、大きな被害を受けます。また新政府艦隊は、上陸作戦で奥羽越列藩同盟の洋式武器の供給源である新潟港を制圧します。敗れた奥羽越列藩同盟の残存兵力は、会津へと撤退しました。 |
 ■長岡城攻防絵図 |
|
|
|
| -仙台藩の降伏- 奥羽越列藩同盟の盟主であった仙台藩は、白川城攻防戦や平潟戦線を戦いますが、新政府軍に比べ装備に劣り各地で敗戦を重ねます。藩境の旗巻峠での戦いに敗れ、領内に新政府軍の侵攻を許した仙台藩は、先に降伏していた米沢藩の降伏勧告を受け入れて降伏しました。 |
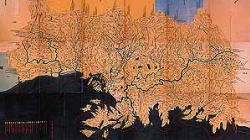 ■仙台 |
|
|
|
| -会津戦争- 新政府軍は、大軍を動員して会津藩への攻撃を開始します。会津藩は篭城して抗戦し、歳若い少年や女性まで戦闘に参加しました。少年兵で構成された白虎隊は、城下の火災を落城と誤認して自刃します。また、城下の武家の妻子達の中には、篭城前に自刃する者も多くいました。このような悲劇が繰り返される中、会津藩は約1ヶ月の抵抗むなしく降伏します。 |
 ■白虎隊自刃之図 |
|
|
|
| -秋田戦争- 最新兵器を装備していた庄内藩は、新政府軍を相手に連戦連勝を重ねます。これに対して新政府軍はアームストロング砲やスペンサー銃を装備した佐賀藩兵を投入しますが、庄内藩は強く新政府軍を次々と撃破していきます。しかし、味方であった米沢藩や会津藩が相次いで降伏し、庄内藩以外の全ての藩が恭順したために新政府軍に降伏しました。 |
 ■秋田戦争 |
|
|
|
| -蝦夷共和国- 旧幕府の艦隊は江戸から脱出して、奥羽越列藩同盟や旧幕府軍の残党を吸収して蝦夷地に入ります。箱館五稜郭を占領して蝦夷地を支配下におきます。この勢力は日本で始めて指導者を選挙で選び、幕府海軍副総裁であった榎本武揚を総裁としました。この蝦夷地に誕生した政権は通称「蝦夷共和国」と呼ばれます。 |
 ■蝦夷共和国首脳 |
|
|
|
| -宮古湾海戦- 新政府は青森に集結して、雪解けを待って蝦夷地を攻めることを決定します。これに対して蝦夷共和国は、宮古湾に停泊中の新政府艦隊に先制攻撃をかけます。新政府艦隊の新鋭艦甲鉄に対して移乗攻撃を仕掛け、甲鉄の奪取を謀りますが失敗に終わりました。 |
 ■宮古湾海戦 |
|
|
|
| -箱館戦争- 蝦夷共和国は、艦隊の旗艦である開陽丸を座礁で失っていました。これによって制海権は新政府軍のものとなります。雪解けを待って、新政府軍は蝦夷へ上陸。約3倍の兵力で侵攻する新政府軍に対して、蝦夷共和国軍は応戦しますが敗走を続けます。ついに五稜郭に追い詰められた蝦夷共和国軍は降伏し、戊辰戦争は終結しました。 |
 ■箱館戦争図 |
|
|
|
| -東京奠都- 明治天皇は、京都を出発して江戸へ行幸します。東西に首都を造るという計画により、明治天皇の到着と同時に江戸は東京と改称されました。次の年にも明治天皇は東幸し、そのまま東京を拠点とします。その後、次々と新政府の行政機関が東京に移転し、事実上東京に首都が移されました。しかし、京都民や反対派に配慮して天皇も政府も遷都を公然発表していないため、天皇は東京に行幸して滞在しているだけということになっています。 |
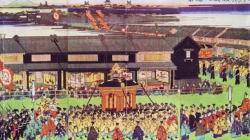 ■東京奠都 |
|
|
|
| -御一新- 新政府(以下明治政府)は、天皇親政に伴い大改革を行います。政治においては三権分立制を採用します。そのほか軍政改革、学制改革、地租改正、断髪令や廃刀令、グレゴリオ暦の採用と急激な改革を行います。この強引な改革が、士族や農民の不満につなかっていきます。 |
 ■地租改正 |
|
|
|
| -廃藩置県- 工事中。 |
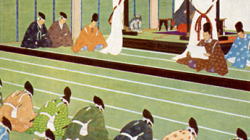 ■廃藩置県 |
|
|
|
工事中
 |
トップページへ |